温度または圧力の変化により、物質の相変化が起こることは、我々の日常生活でも見うけることです。 よく見うける例としては、液体を熱すると蒸発してガスとなることや、磁石を熱すると磁力がなくなることなどがあります。
日常的にはあまり見うけられる例ではありませんが、ある温度以下では混和されるが、その温度以上では混和されない2元流体混合物システムがあります。 Kenneth Wilsonが1970年に発表した、濃縮に関する物理学の集大成となる再正規化群論によれば、多くの異なるシステムの臨界挙動には、それぞれに特有の相互作用からは独立した共通の性質があることが示されています。 Wilsonは、この業績により1982年のノーベル物理学賞を受賞しました。
Wilsonの優れた発見の一つは、多くの異なるシステムにおいて、臨界のべき指数が同じであることを示したことです。 強磁性体、液-気相転移、2元流体混合物等において、3次元モデルにおける臨界べき指数は、それぞれ1.24および0.63となります。
ここでは、Corti、MineroおよびDegiorgioの業績を更に進めた、DietlerおよびCannellの業績の追試を行いました。 水と非イオン性界面活性剤の2元混合物の臨界現象が、予想されたべき指数と一致することを示します。
2元流体システムにおいて、浸透性はASTRAで計算されるモル分子量に比例し、相関長さはASTRAで計算されるrms半径に比例することが分かりました。
図1には、浸透性と相関長さが温度の関数としてプロットされています。 次にこれから、臨界温度(Tc)と臨界べき指数とを求めます。 両対数目盛に、減少温度(1-T/Tc)に対してデータをプロットすると図2に示すように直線が得られます。 これより、臨界温度はTc=315.51K、臨界べき指数は=1.27、=0.635となり概ね理論値と一致します。
DAWN EとASTRAとを用いて、臨界現象の実験を行い、古典的な理論を実証することができました。 DAWN Eがなければ、この実験は数ヶ月かかったと思われますが、DAWN Eの使用により、1日あるいは数時間で実験が可能となりました。
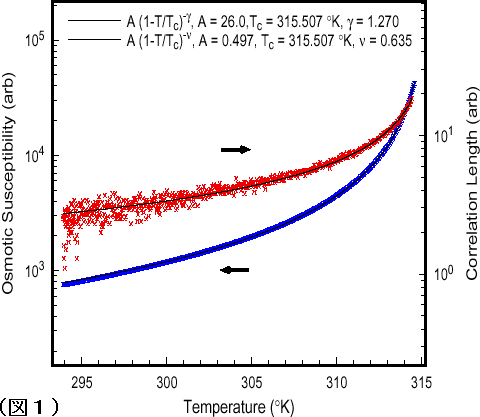
図1:浸透性と相関長さは、温度がTc(315.507K)に近づくにつれて分岐していきます。 この現象は、「critical opalescence」または「clould point transition」と呼ばれています。
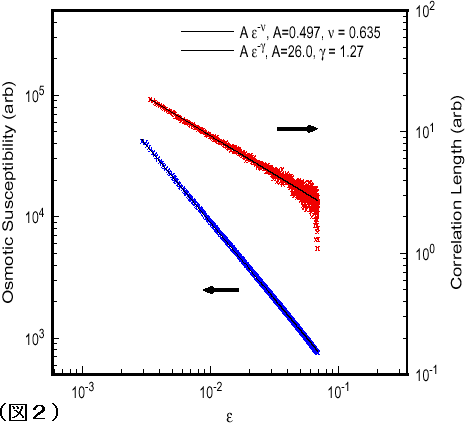
図2:浸透性と相関長さを減少温度に対してプロットしました。この傾きから臨界べき指数が得られます。